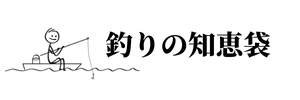このような疑問にお答えします。
深海に生息し、謎の多いサメである「メガマウス」。
日本でも、時折メガマウスが漁船の網にかかったというニュースが流れますよね。
大きな体に見合う、大きな口が特徴のメガマウス。
実は深海に住むメガマウスは、世界中をみても、目撃情報が少ない魚です。
今回はそんな深海魚「メガマウス」とはどんな魚なのか、その生態について深堀していきたいと思います。
深海に生息しているため、飼育などはできず、まだまだ未知の部分も多いメガマウス。
人間に害があるのかなども合わせてご紹介いたしますので、是非参考にしてみてくださいね。
目次
メガマウスとは?

時折発見され、ニュースになることもある「メガマウス」。

このような疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。
まず最初に「メガマウス」とはどんな魚なのかについてご紹介いたします。
メガマウスってどんな魚?
メガマウスは、1976年に初めて発見された非常に珍しい深海性のサメです。
メガマウス(Megamouth Shark)の学名はMegachasma pelagios。
比較的最近発見された深海魚です。
釣り人
「生きた化石」とも称される幻の深海魚なんですよ。
名前の通り、体に不釣り合いなほど大きな口(mega mouth)を持っているサメですね。
基本情報
- 分類:メガマウス科メガマウス属(唯一の種)
- 体長:最大で約5〜6m
- 体重:1トン前後
- 生息水域:世界中の深海(200〜1,000m)
- 生息地域:特に太平洋やインド洋での目撃が多い。
- 発見例:世界でも100例程度
このような魚です。
メガマウスは、メガマウス科メガマウス属という分類のサメで、唯一の種です。

なぜ“幻の深海魚”と呼ばれるのか?
メガマウスは、別名「幻の深海魚」とも呼ばれています。
なぜそう呼ばれているのかについてもみていきましょう。
幻の深海魚と呼ばれる理由
- 発見数が極めて少ない。(2025年時点で世界で100例ほど)
- 発見されるのは、定置網に偶然かかる、打ち上げられるなど稀なケース。
- その生態の多くが未解明。
調査の機会が限られているため、なかなか生態が解明されていないのが現状ですね。

世界中に生息しているものの、人がダイビングなどでは潜ることのできない水深にいるため、なかなか見ることができないサメなんですよ。
世界で記録されたメガマウスの個体数は、発見から約半世紀を経た現在でも100例程度。
これは同じく珍しい深海生物であるラブカやリュウグウノツカイと比べても、圧倒的に少ないといえます。
おすすめメガマウス動画
出典引用:YouTube動画(さかなクンちゃんねる - FISH BOY - Sakana-kun)
珍しいサメである「メガマウス」。
魚を愛することで知られている「さかなクン」のYouTube動画でも紹介されています。
この動画でも、なかなか見ることのできない希少性の高いサメであることがわかりますね。
メガマウスの生態

出典引用:カラパイア
メガマウスの生態についてもおさえておきましょう。
メガマウスは、他の深海魚と同様、謎に包まれた部分が多いサメです。
現在わかっている範囲で、メガマウスとはどんな生態を持つサメなのかご紹介いたします。
特徴的な外見
メガマウスとは、どんな外見をしているサメなのかについてもおさえておきましょう。
メガマウスの外見
- 巨大な口。(半開きの状態でも直径1メートル以上)
- 丸い頭部。
- 小さい歯。
- ずんぐりとした体型。
このような特徴を持っています。

メガマウスの歯は、餌を噛むためではなく主にプランクトンの濾過に使われていますよ。
メガマウスの生息域と深海での暮らし方
メガマウスの生息域についてみていきましょう。
メガマウスは、世界各地の温暖な海域の深海に生息しています。
特に日本・台湾・フィリピン・アメリカ西海岸などでの目撃や捕獲例が報告されていますよ。

現在判明している生息地域
- 太平洋やインド洋(日本・台湾・フィリピン・アメリカ西海岸)
- 200〜1,000mの深海
このような場所で目撃、生息していると考えられています。
冷水域でも活動可能な体構造をしているため、様々なエリアで目撃されています。
日本での主な目撃・捕獲例
- 1994年(静岡県):生きた個体を冷凍保存し、展示。
- 2007年(三重県):定置網にかかり、国内メディアでも話題になる。
- 2011年(静岡県沼津市):深海水族館の学術研究用に利用された「。
実は日本近海では、比較的メガマウスの発見頻度が高いんですよ。
特に静岡や沖縄などでの報告が複数あります。
おすすめ動画
出典引用:YouTube動画(CBCニュース)
日本は世界の中でも有数のメガマウスが目撃されている地域です。
こちらは漁船の網にかかって、捕獲されたメガマウスのニュース動画。
漁船にかかった、生きているメガマウスを見ることができます。
元気に動いているメガマウスを見ることのできる貴重な機会ですね。
日中と夜で移動する?垂直移動の謎
メガマウスは昼の時間帯、水深200〜1,000mの深海に潜んでいます。
しかし夜になるとプランクトンを求めて、浅い海(100〜200m)まで浮上する「垂直移動」を行うことが分かっています。
これは“ディープスキャッタリングレイヤー”と呼ばれる生物群に合わせた動きと考えられています。

メガマウスの、主なエサはクラゲやプランクトン。
巨大な口で海水をろ過して摂取しています。
メガマウスは危険なの?人間への影響と安全性

出典引用:ガラパイアHP
メガマウスは深海に生息するため、私たちが遭遇する確率は低いです。
しかしメガマウスは名前にシャークとつくように、サメの一種です。
サメというと、危険なイメージが強いですよね。
メガマウスは人間に危害を及ぼすサメなのかどうかについても知っておきましょう。
おとなしい性格のメガマウス
メガマウスは英語名に「シャーク」と付いているため、危険と思いがち。
しかしメガマウスは非常に温和な性格のサメで、人間に危害を加えることは基本的にありません。
これまでに人を襲ったという報告もないんですよ。
メガマウスの最大の特徴である大きな口も、小さなプランクトンやクラゲを効率的に濾し取るためのもので、鋭い歯は持ち合わせていません。
主な餌
- プランクトン
- クラゲ
- カイアシ類
これらがメガマウスの餌です。
そのため、ホホジロザメなどの鋭い歯で大型の獲物を狙うサメとは異なり、ジンベエザメやウバザメのような“濾過摂食型のサメ”なのですね。
ジンベエザメやウバザメと並ぶ三大濾過摂食ザメだと考えられています。

メガマウスと他の深海ザメとの違いとは?
同じ濾過摂食を行うジンベエザメやウバザメと、メガマウスの違いについてもみていきましょう。
メガマウスの特性
- ジンベエザメやウバザメより深海に生息する。
- 夜行性。
- 外見でも唇のような肉厚な口周りが特徴的。
他のサメとは、一線を画すような生態ですね。
メガマウスは「深海性のサメ」に分類されます。
そのため体の構造にも、深海適応が見られます。
メガマウスの深海適応
- 筋肉が柔らかい。
- 泳ぐ速度が遅い。
- 光を感知しやすい目の構造。
- 冷水域でも活動可能な体構造
深海の圧や暗さに適応するメガマウスは、これらの深海適応があることがわかっています。
またメガマウスの体表には、発光器官があると考えられています。
そのため発光器官があるため、暗い深海でも行動が可能なのですね。

メガマウスの飼育と保護の必要性

出典引用:WEB魚図鑑
ここまではメガマウスの生態についてご紹介しました。

水族館でみることができたらいいのにな、という方もいらっしゃるかと思います。
では実際に水族館などで飼育は可能なのか、についてもみていきましょう。
飼育は困難
発見された例も少ないメガマウス。
捕獲自体が困難なため、メガマウスの飼育例は極めて少ないです。
また飼育を試みた例をみても、長期飼育には成功していません。
メガマウスは通常深海という特殊な環境に適応していて、浅海の水圧や水温の変化に耐えられないために、長期飼育は困難なのです。
観察可能な施設はあるのか?
生きているメガマウスを水族館などの施設で見ることは、現在できません。
しかしながらメガマウスの標本を観察できる施設は、
- 静岡県沼津市の「深海水族館」
- 過去に捕獲された個体を標本展示している研究機関
これらの施設でメガマウスの標本を見ることができます。
研究機関は、なかなか一般の人が入ることは難しいため、標本を見たいという方には静岡県沼津市の「深海水族館」がおすすめですよ。
おすすめぬいぐるみ
ZHONGXIN MADE メガマウスのぬいぐるみ
こちらはメガマウスを模したぬいぐるみです。
大きな頭と大きな口、やわらかい感触で、抱き心地もよい一品。

実際に目で見ることが難しいメガマウスなので、ぬいぐるみがあると知って、私は思わず購入してしまいました。
メガマウスは絶滅危惧種?保護の必要性と現在の評価

メガマウスが発見されたのは、比較的最近です。
地球温暖化や環境破壊などが叫ばれている現在、メガマウスは保護の対象なのかなどについてもみていきましょう。
step
1IUCNレッドリストでの位置づけ
深海深くに生息しているメガマウス。
メガマウスは目撃情報も少なく、まだまだ謎の多いサメの一つです。
そのためIUCN(国際自然保護連合)のレッドリストにおいても、メガマウスは「情報不足(Data Deficient)」として分類されています。
メガマウスはどのくらい生息しているのか、またその生態に関するデータが極めて乏しく、正確な評価ができないのが現状ですね。
step
2保護のための国際的な取り組み
現在のところ、メガマウスに特化した保護活動や国際的な条約はありません。
しかし希少性の高いメガマウスは、まだまだ生態についてわかっていないことばかりで、どのように保護をしたらいいのかなども決まっていません。
そのため発見された個体を適切に記録・研究し、生態の理解を深めることが、将来的な保護施策に繋がると期待されています。
【深海魚】メガマウスってどんな魚?神秘的な生態とその秘密に迫る!:まとめ

今回は深海魚であるメガマウスについて、ご紹介しました。
水深200~1000mに生息するメガマウスは、比較的最近発見されたサメの一種で、発見された例も少なく、まだまだ謎の多いサメです。
ジンベエザメやウバザメと並ぶ三大濾過摂食ザメであるメガマウスは、おだやかな性格なため、人間に危害を与えることもありません。
なかなか見る機会のないメガマウスですが、今後研究が進み、その生態が解明されるのが楽しみですね。