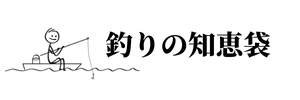このような疑問にお答えします。
海へ釣りに行って、何度遭遇しても「ぎょっ」っとしてしまうウミケムシ。
その見た目からしても苦手という方が多いかと思いますが、厄介なのが「毒」を持つことですよね。
私の友人はウミケムシを釣り上げた際に、毒があると知らずに触ってしまい、刺されてしまって大変だったと言っていました。
今回はそんな毒のある「ウミケムシ」がどこにいるのかについてご紹介したいと思います。
海にあまり行かないという方は、ウミケムシという生物にあまりなじみがないかもしれません。
しかしウミケムシのように毒のある生物の発生場所を知っておくことは、今後釣りをはじめたり、海辺に行くことがある方にとって重要な情報です。
また刺されてしまった場合の対処法についてもご紹介しますので、是非参考にしてみてくださいね。
目次
ウミケムシってどんな生物?その正体とは

まずはウミケムシとはどんな生物なのかについてみていきましょう。
ウミケムシ(学名:Hermodice carunculata)は、多毛類(ゴカイやイソメの仲間)に属する生物です。
からだの構造なども変わっているので、最初におさえておきましょう。
ウミケムシとは
ウミケムシの基本的な情報は以下の通りです。
ウミケムシの基本情報
- 分類:環形動物門 多毛綱 ウミケムシ科。
- 体の構造:体の両側に無数の剛毛(毒針)を持つ。
- 生息地:磯場、砂泥地、防波堤、港湾などの沿岸部。
- 習性:夜行性で、底生生物を捕食する。
このような生物です。

ゴカイの仲間で、様々な種類がいます。
体長は10cm〜30cmほどで、細長い円筒形の体を持ち、体の両側に無数の剛毛(毒針)を生やしています。
日本全国の沿岸に生息しているため、投げ釣りなどをしていると、釣れることもありますよ。
毒があるため、釣れてしまった場合には、触らないように注意しましょう。
体の構造
ウミケムシの構造について最初にみていきましょう。
ウミケムシの構造
- 環節
- 剛毛
ウミケムシは、このような構造を持つ生物です。
環形動物の一種であるウミケムシの体は、多くの環節(セグメント)に分かれていますよ。
各環節には剛毛(せつ毛、または不規則に生える毛状の突起)があります。
釣り人
この剛毛は、移動、捕食、防御などに使われています。
ウミケムシの大きさは種類によって異なりますが、大型の種類を除き10㎝程度ですね。
ウミケムシの体色
ウミケムシは種類によって、体色も様々で鮮やかな色を持つ種類から、地味な色をしたものもいます。
周囲の環境に溶け込むような色や模様を持ち、カモフラージュして生息しているのです。

分布と生態

生息地と生態についてみていきましょう。
生息地
ウミケムシは世界中の海洋に広く分布し、浅い潮間帯から深海までさまざまな環境に適応しています。
比較的温暖な場所を好むものが多く、日本では本州中部以南に生息しています。
岩礁、砂泥底、海藻の根元などによくいて、これらの場所で予期せず釣れてしまうことも多いので注意しましょう。
生態
ウミケムシは、基本的に夜行性の生物です。
そのため昼間は、海底の砂地などに隠れています。
しかし顔は出しているので、餌を見つけると飛び出してきます。

また夜はゴカイに比べると、かなり早いスピードで海中を動き回っていますが、これは餌を得るためではないんだそう。
夜に動き回る理由が解明されていないところも、面白い生物と言えるでしょう。
ウミケムシの食性
次にウミケムシの食性についてみていきましょう。
ウミケムシの食性
- 肉食性
- 草食性
- 腐食性
ウミケムシは種類によって、食性が異なります。
プランクトンや小型の無脊椎動物を捕食する種類や、デトリタス(有機物の死骸や分解物)を食べる種類がいますよ。
釣り人
ウミケムシは貝類や死骸などを食べるスカベンジャー(腐肉食者)としての役割も持っていて、海の生態系に欠かせない生物です。
攻撃的な性質はありませんが、餌をみつけると飛び出してきて釣り針にかかることが多いウミケムシは、釣り人にとっては厄介な存在ですね。
繁殖と成長過程
ウミケムシは卵生で、繁殖期になると海中に卵を放出します。
繁殖期は通常秋〜冬で、一度に大量の卵を産みます。
卵は海中に浮遊し、孵化した幼生はプランクトンとして海を漂っているんですよ。

幼生はプランクトンとして生活し、成長すると海底に定着してウミケムシへと変化。
成長過程は比較的早く、幼生から成体に成長するまでに数ヶ月から1年ほどです。
ウミケムシの身の守り方
全ての種類ではありませんが、ウミケムシは、毒素を持っています。
敵に遭遇した時には、毛を逆立てて、毒素を使って攻撃します。
これらの毒素は剛毛に含まれており、触れると痛みや炎症を引き起こすので注意しましょう。
そのためウミケムシを見かけても、素手で触ることは厳禁。
魚ばさみなどで対処しましょう。
また剛毛などは、物理的な防御機構としても有効活用されています。
海毛虫の天敵
ウミケムシ天敵は、主にエビやカニなどの甲殻類です。
ベラなどの魚もウミケムシを捕食する魚なので、これらの魚も天敵ですね。
ウミケムシを捕食している生物は多いため、防御と攻撃をするために毒針がついています。
ウミケムシの種類

ウミケムシの種類についてみていきましょう。
ウミケムシは、実は100以上もの種類が確認されている生物です。
代表的なウミケムシ
- ウミケムシ
- ハナオレウミケムシ
- セスジウミケムシ
- セナジリウミケムシ
これらが有名なウミケムシです。
ゴカイとよく似ているものもいますが、間違って触ってしまうと毒にやられてしまいます。
ゴカイだと思っても、十分注意するようにしましょう。
step
1ウミケムシ
学名「chloeia flava」と呼ばれるものが、日本で一番よくみられるウミケムシです。。
ウミケムシの特徴
- 毒を持っている。
- 体の色は赤色。
- 体長10㎝程度。
これらの特徴を持ちます。
step
2ハナオレウミケムシ
最もゴカイに似ているのが、ハナオレウミケムシです。
ハナオレウミケムシの特徴
- 毒を持っている。
- 体の色はピンク色。
- 細長い。
これらが特徴です。

石の下などの浅瀬に生息しているので、現地で餌を調達する際はゴカイと間違えないよう、十分注意が必要です。
step
3セナジリウミケムシ
毒がありそうな見た目をもつのが、セナジリウミケムシです。
セナジリウミケムシの特徴
- ウミケムシより長い。
- 体の横に毒を持っている。
- 体色は赤で、白い線のような模様がある。
このような特徴があります。
ハナオレウミケムシと違い、見た目から危険を感じるウミケムシですので、見かけたら触らないようにしてくださいね。
step
4ダイオウウミケムシ
ウミケムシの種類の中でも、最も大きいのがダイオウウミケムシです。
ダイオウウミケムシの特徴
- 体長は30㎝を超えることもある。
- 水中だけでなく陸に上がっても生活できる。
- ネズミを食べることもできるほど獰猛。
これらの特徴をもちます。

大きいだけでなく、素早く、危険なウミケムシですので、絶対に素手で触らないようにしましょう。
ウミケムシの危険性

ウミケムシとはどんな生物なのか分かったところで、その毒の危険性や対処法などについてもおさえておきましょう。
ウミケムシ毒とは
ウミケムシ毒は、海毛虫(Polychaete)の一部の種類が持つ毒素のこと。
多くは無害ですが、一部の海毛虫はさわると毒のある触手(毒針)がガラス繊維のように皮膚に刺さってしまいます。
ウミケムシの剛毛の毒はコンプラニンとよばれる強い毒性があります。
刺されると激しいかゆみや痛みが続くので注意が必要です。
ウミケムシに刺されるとどうなるの?

ウミケムシに刺されてしまうと、どうなるのかについて最初におさえておきましょう。
ウミケムシ毒は、ウミケムシの剛毛に含まれており、この毒素は、皮膚に接触することで刺激や炎症を引き起こします。
ウミケムシ毒の成分と作用
- 痛み:刺された部位に強い痛みを伴う。
- 炎症:刺された部位が赤く腫れる。
- かゆみ:かゆみを伴い、掻いてしまうと症状が悪化する。
- 発疹:場合によっては発疹が現れることもあります。
毒素の具体的な成分は種類によって異なりますが、このような症状がおこることが多いです。
刺されてしまったら、適切に対処し、病院へ行くようにしましょう。
ウミケムシに刺されないためには
万が一ウミケムシに刺されてしまったら、痛みやかゆみ、腫れなどの症状がでてしまいます。
そのため、ウミケムシの被害にあわないように対策することも重要です。
ウミケムシ対策
- 長袖、長ズボンの着用。
- 手袋の着用。
- 釣行中も周囲に注意する。
- ウミケムシの出没するエリアの情報収集。
これらをすることで、ウミケムシから身を守りやすくなります。
事前にウミケムシが出るエリアなのか調べておき、よく出没するエリアに行く際には、肌の露出を避けるといいでしょう。
季節によっても出没状況が異なるので、情報収集は必須ですね。
ウミケムシを釣ってしまったら
ウミケムシは投げ釣りなどをしていると、予期せず釣れてしまうことがありますよね。
釣ってしまった場合、どう対処したらいいのかをしらないと、刺されてしまうかもしれません。
釣ってしまった時にどうしたらいいのかについて、しっかりと頭に入れておきましょう。
ウミケムシが釣れた場合
- 仕掛けを振り回さない。
- 仕掛け類はあきらめてハリスを切って、ウミケムシを海に落とす。
- 魚ばさみでつかむ。
このように対処すると刺されずにすむので、慌てず冷静に対処するようにしましょう。
ウミケムシに刺された場合の対処
どれだけ注意していても、ウミケムシに刺されてしまうこともありますよね。
そんな場合の対処法についてもおさえておきましょう。
万が一ウミケムシに刺されてしまったら、病院に行く。
これが最適な方法ですが、病院へいくまで何も対処せずに刺されたままでいると悪化してしまうこともあります。
まずは、応急処置をしてから向かいましょう。
応急処置
- ウミケムシを魚ばさみなどで取り除く。(素手で触らない。)
- 剛毛を除去する。
- 刺された場所を洗浄する。
- 冷却する。
- 病院を受診する。
これらがウミケムシに刺されてしまった際の応急処置です。
step
1ウミケムシを魚ばさみなどで取り除く
刺されてしまった場合、慌てず冷静にウミケムシを取り除くことが重要です。
慌てて、素手で払ってしまうと、手を刺されてしまいます。
取り除く際は、絶対に素手で触らず、魚ばさみなどを使って行いましょう。
step
2剛毛を除去する
ウミケムシに刺されてしまうと、皮膚に剛毛が残ってしまいます。
ピンセットやテープを使って、残っている剛毛を慎重に取り除きましょう。

ゴム手袋などをして、慎重に行いましょう。
step
3刺された患部の洗浄
剛毛を除去したら、患部を流水でよく洗いましょう。
近くに水道がない場合も、ペットボトルの水などで洗い流すことが重要です。

水で患部を洗う効果
- 毒を洗い流す効果。
- 患部の冷却。
これらの効果を期待できます。
また石鹸を持っている場合は、使用して洗浄することも効果的です。
毒を洗い流し、患部を清潔にしておくようにしましょう。
step
4冷却
患部を洗い流した後は、冷たいタオルや氷で冷やすようにしましょう。
患部を冷やす効果
患部を冷やすことで、
- 痛みを感じにくくする。
- 腫れの軽減。
これらの効果を期待できます。
これはウミケムシ毒に限らず、蜂やアブに刺された場合にも有効です。
ただしエイの毒針のようなタンパク毒には冷却は逆効果になりますので、それぞれの毒に合う対処法を行いましょう。
step
5医師の診察
患部の冷却をした後は、病院へ行って医師の診察を受けるようにしましょう。
医師の診察を受け、抗ヒスタミン剤などを処方してもらって服用します。
特に症状が重い場合は、速やかに医療機関を受診することが重要です。
釣り人
万が一刺された場所が、顔や目の場合は、必ず病院に急行しましょう。
大丈夫だと自己判断せず、素早い受診が身を守ることにつながります。
おすすめ魚ばさみ
第一精工 フィッシュグリップ ガーグリップMCカスタム ブラック
こちらは第一精工のフィッシュグリップです。
先端部は獲物の下顎をしっかり挟むことができる形状になっていますよ。
またホルスターはハンガーでバッグやゲームベスト、タックルキャリアー、バッカンの枠等に装着可能なのも嬉しいところ。

おすすめガムテープ
ニチバン 布テープ 50mm×25m巻 121-50 黄土
こちらはニチバンの布ガムテープです。
べたべたしすぎず、手でも切りやすいのが嬉しい一品。

紙製のテープに比べ、布製はしっかりとしているので、梱包などでも活躍してくれますよ。
おすすめピンセット
ピンセット 精密 [4本セット(4種類)] 精密ピンセット 【おだ商店】
こちらはおだ商店のピンセットセットです。
ピンセットの先の形状が4種類あるので、用途によって使い分けることができる一品。
プラモデルなどを組み立てや、食玩のシールを貼る際ににも重宝しますよ。

用途によって使い分けもできますし、細かいものもつかみやすいので、子供のおもちゃのシール貼りなどに重宝しています。
ウミケムシの生息地

ウミケムシの毒性についてここまではご紹介しました。
では実際ウミケムシはどんなところを好んで生息しているのでしょうか。
先程も軽く触れましたが、ここではもっと具体的にみていきましょう。
ウミケムシがいる場所をおさえておくことで、対策をしやすくなりますよ。
日本でのウミケムシの分布
ウミケムシは、世界中の温暖な海域から熱帯・亜熱帯の沿岸部に広く分布しています。
日本でも全国の海域で確認されています。
日本国内の分布
- 太平洋側の沿岸部(千葉県〜九州)。
- 瀬戸内海(波が穏やかで、砂泥底が多いため)。
- 沖縄・南西諸島(温暖な海域で個体数が多い)。
日本では本州、四国、九州、沖縄を中心に、沿岸部のさまざまな場所でみることができますよ。
特に、温暖な海域ほど個体数が多くなる傾向があります。
ウミケムシは水温が15℃以上の環境を好むため、冬の寒冷な海域では活動が鈍くなるんですね。
水温が安定している温暖な地域では、一年中活発に活動しています。
一言メモ
世界の分布
- 太平洋全域(日本、東南アジア、オーストラリア沿岸など)
- インド洋(インド、スリランカ、アフリカ東海岸など)
- 大西洋沿岸(アメリカ東海岸、カリブ海、地中海など)
ウミケムシは、日本だけでなく世界中の海に広く生息しています。
特に、カリブ海や地中海沿岸では、サンゴ礁地帯に多く見られますね。
ウミケムシの好む環境
ウミケムシは砂泥地や岩場など、海底の堆積物が豊富な場所に多く生息します。
よく見られる環境
- 磯場・岩場:海藻が多く、隠れやすい環境。
- 港や防波堤周辺:堆積物が多く、エサが豊富。
- 砂泥地の海底:海底に潜りながら生活する個体もいる。
- 河口付近:淡水と海水が混ざる汽水域でも確認される。
これらの場所をウミケムシは好み、生息しています。
釣り人
夜行性のウミケムシは、夜になると海底から浮上して活動が活発になるため、夜釣りをする際には注意しましょう。
ウミケムシはどこにいる?よくみられる環境を知って対策しよう!:まとめ

今回は釣れると厄介なウミケムシについてご紹介しました。
ウミケムシは触れてしまうと痛みやかゆみを伴います。
そのためウミケムシがどんな場所を好むのか、また活性化する時間帯などを頭にいれておくほか、刺されないための対策や万が一の際の応急処置について知っておく必要があります。
是非今回ご紹介したウミケムシの好むエリアや環境などを参考にして、安全に釣りを楽しんでくださいね。